「洗濯物の山ができて、片付ける気が起きない…」
「子どもが洗濯物の山の上で遊んでしまう…」
そんな経験はありませんか?
今から25年ほど前、私はまさにこの状況にいました。当時、親族100人ほどが集う大家族の本家の嫁で、環境の変化に弱い自閉症の息子を育てる日々でした。
おしゃれで完璧な部屋でなくてもいい。
でも、視覚的にごちゃついていたり、環境が頻繁に変わったりすると、息子のパニックにつながってしまいます。
仕事と育児で心身ともに疲れ果てた私にとって、部屋に散乱する子どもの小さな洗濯物は、どうすることもできない重荷でした。
そんな私がたどり着いた結論は、「そもそも洗濯物の山を作らなければいい」。
このシンプルな発想から生まれた、洗濯システムをご紹介します。
山を作らないための4つのステップ
このシステムの一番のポイントは、洗濯が終わった後です。
洗濯機から出した洗濯物は、まず屋外の物干し竿に干します。わが家はベランダに雨が直接吹き込まないため、雨の日でも外に干すのが基本です。
ここからが、このシステムを成功させる鍵となる4つのステップです。
- 部屋別に干す
ピンチハンガーやハンガーを、子ども部屋用、私の寝室用、その他(洗面所・台所)用と部屋ごとに分けて使用します。
これによって、後から仕分けをする手間が省けます。
- 収納の近くに部屋干しする
わが家では、無印良品の収納シェルフを使い、息子の成長に合わせて高さを変えてきました。
このシェルフの取っ手や、隣の突っ張り棒に洗濯物を引っかけて部屋干しします。
収納場所のすぐそばに干すことで、次の工程が劇的にスムーズになります。
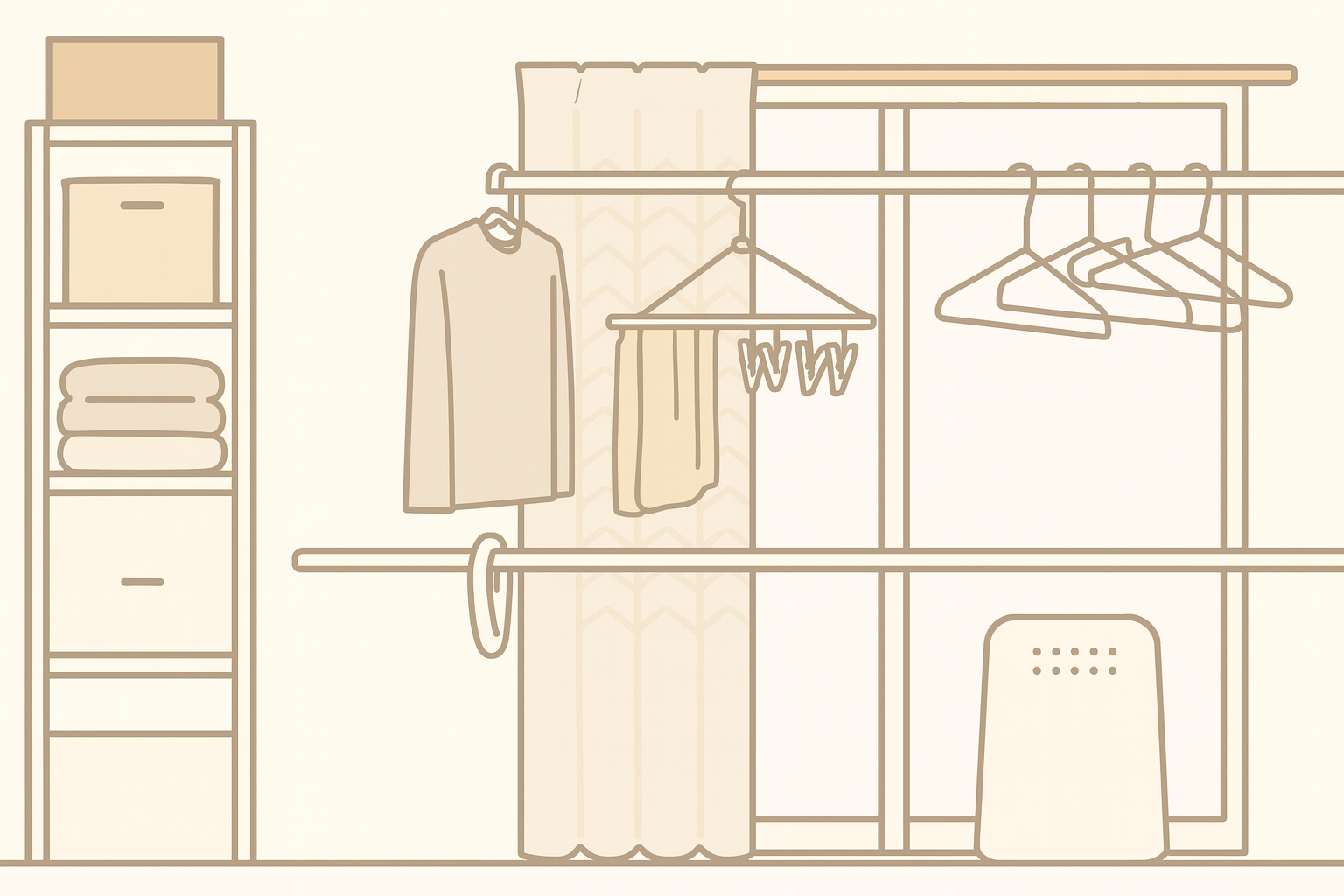
- 畳んで直接収納する
ハンガーから外した洗濯物は、床に置かずにその場で畳み、直接引き出しにしまいます。
これは、アパレル店での勤務経験がない方には少し練習が必要かもしれません。
コツは、重力を使って衣類を伸ばすイメージで、立ったまま畳むこと。
シワは濡れているうちに伸ばしておくと、よりきれいに仕上がります。
引き出しを開け、その中にしまう衣類だけを選んで畳んでしまう、という動作を繰り返すだけです。
入れる引き出しの数は限られているので、数回の動作で片付けは完了します。
「片付けなきゃ!」と意気込む必要はありません。部屋に入ったついでに、その部屋に干してある洗濯物を畳んでしまうだけで、いつの間にか洗濯物はなくなっています。
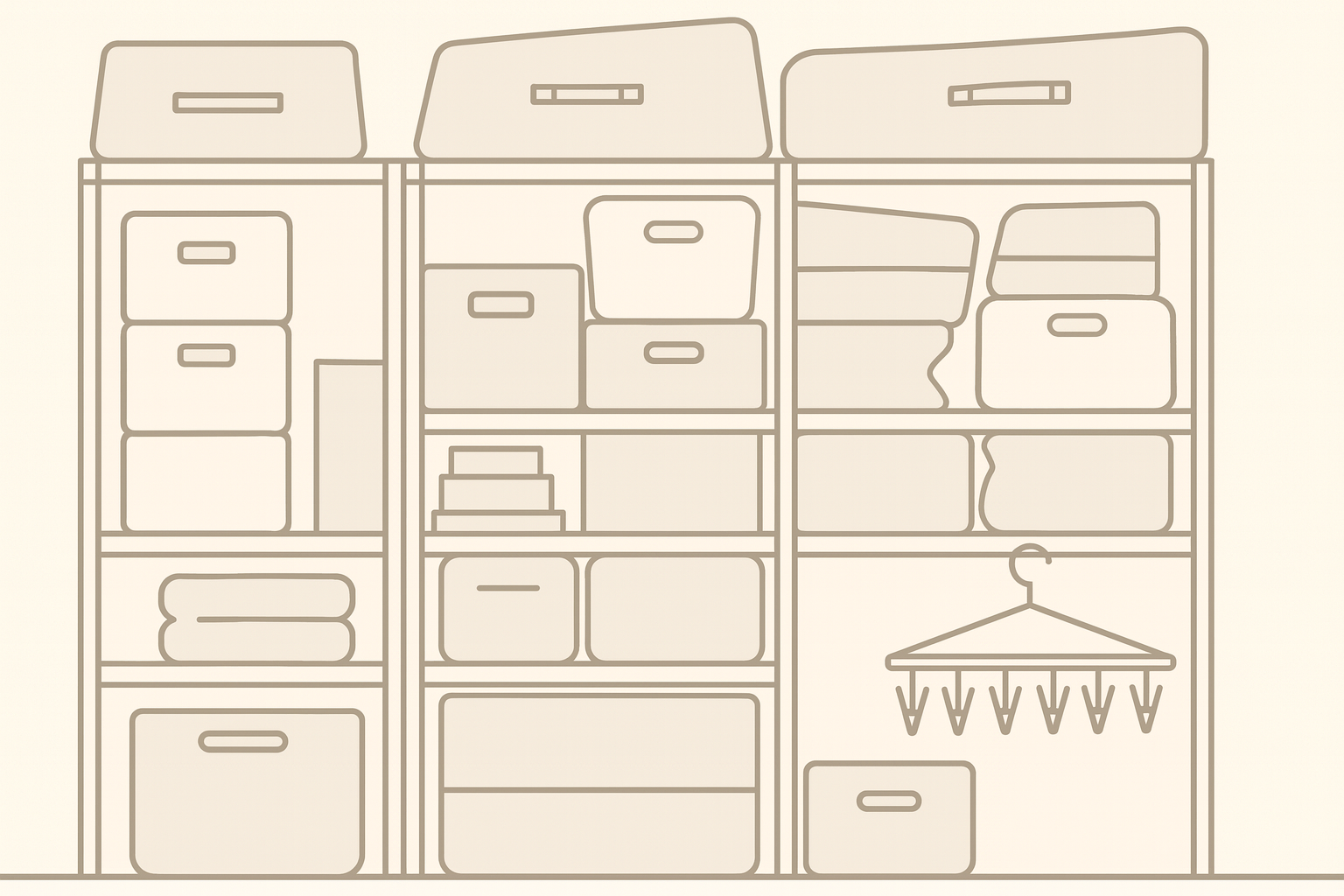
- ピンチハンガーは2つずつ用意する
部屋干し用と外干し用で、あらかじめピンチハンガーを2つずつ用意します。
部屋干ししている洗濯物を畳み終えてハンガーが空になったら、外干し中のハンガーと交換します。
空になったハンガーに、次の洗濯物を干す、というローテーションを繰り返します。
このシステムのメリット
大雨の日を除けば、部屋干しする前には、ある程度乾くので、自分の都合の良いタイミングで片付けができます。
「外干し用のハンガーが汚れるのでは?」と最初は心配しましたが、25年経っても、このローテーションのおかげで問題なく使えています。
洗濯物は外干し1日、部屋干し1日と、合計2日かけて干すことになるため、生乾きの嫌な臭いがつくこともありません。
何より、床に洗濯物が散らからないため、最大限に床面積を確保できます。子どもがゴロゴロ寝転がったり、おもちゃを広げたりしても安心です。
完璧な家でなくても、家事を少しでも楽にしたい方へ。
この洗濯システムを心からお勧めします。
私の他の活動はこちら
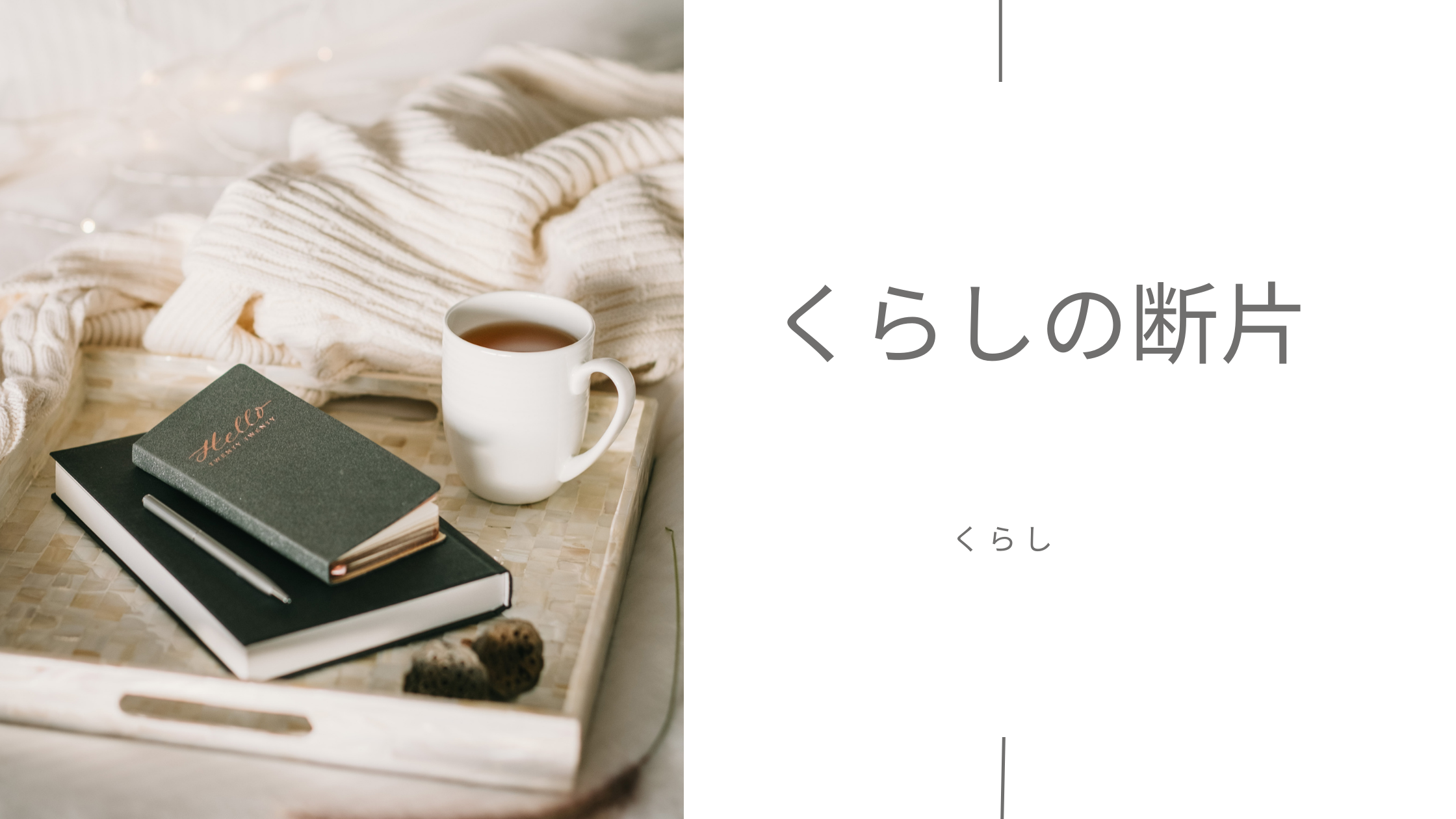


コメント