物は資産か、それとも負債か
暮らしの中にある「物」は、ただの荷物ではなく 資産 と考えることができます。
インフレが進めば物の価値も上がるし、必要な時にすぐ使えれば、生活を豊かにする力になります。
ただし、しまい込みすぎて「どこに置いたか分からない」状態になれば、それは資産ではなく 負債 です。
置き場所を占領するだけで、使えないのですから。
若者とシニアで違う、片付けの正解
- 若い世代:断捨離で頭をスッキリ。「必要になったらまた買う」が正解。
- 年金世代:部屋をスッキリ収納しつつ、「必要な時にさっと出す」が正解。
お片付けの話になると、必ず出てくる断捨離派?収納派?問題ですが、私は上記のように
年齢やライフスタイルによって「物との付き合い方」は変わると考えています。
なぜなら若い世代は、これから効率よく稼いでいつでも買える状態を目指すことが正解だったりするからです。
逆にシニア世代は、インフレで決まった収入の中、いかに今ある資産を有効に使って生活するかが正解であることが多いからです。
覚えられる範囲が資産の上限
収納は「覚えられる範囲」がちょうどいい。
必要な時に、どこにあるか思い出せない物は、もう「ない」のと同じです。
- ラベルを貼っても、貼り忘れたり入れ替え時に混乱する
- 完全に隠す収納だと、思い出せずに埋もれてしまう
だからこそ、「見て思い出せる」収納が大事になります。
心理学が教える「繰り返し見る効果」
人間は 何度も見たものを自然に記憶しやすい 性質があります。
心理学的には以下のように説明されます。
- 単純接触効果(ザイアンスの法則)
繰り返し目にすることで、その情報への親近感や記憶が強化される。 - 再認記憶の強化
視覚的なヒント(透けて見える中身)に触れることで、「あ、ここにあった」と思い出す回路が活性化する。 - 長期記憶への定着
同じ物を何度も目にすると、短期記憶から長期記憶へ移りやすくなる。
この仕組みを利用すると、収納場所を「自然に覚える」ことができるのです。
つまり、繰り返し目にすることが“覚える仕組み”になるのです。
半透明の収納ボックスの力
人間は 何度も見たものを記憶しやすい もの。
半透明のボックスや引き出しにすると、透けて見える中身から連想が働き、自然と記憶に定着します。
私が使っているのは、こういう半透明タイプの収納ケースです。
中身がうっすら見えるので「思い出す収納」としてとても便利。
(参考までにリンクを貼っておきます)
「必要な時に思い出せる収納」は、暮らしに安心感を与える資産そのものです。
あなたの物たちは資産ですか?負債ですか?
次回は「実際に目の前のものをどれくらい片付けるか」という視点で考えてみます。
私の他の活動はこちら
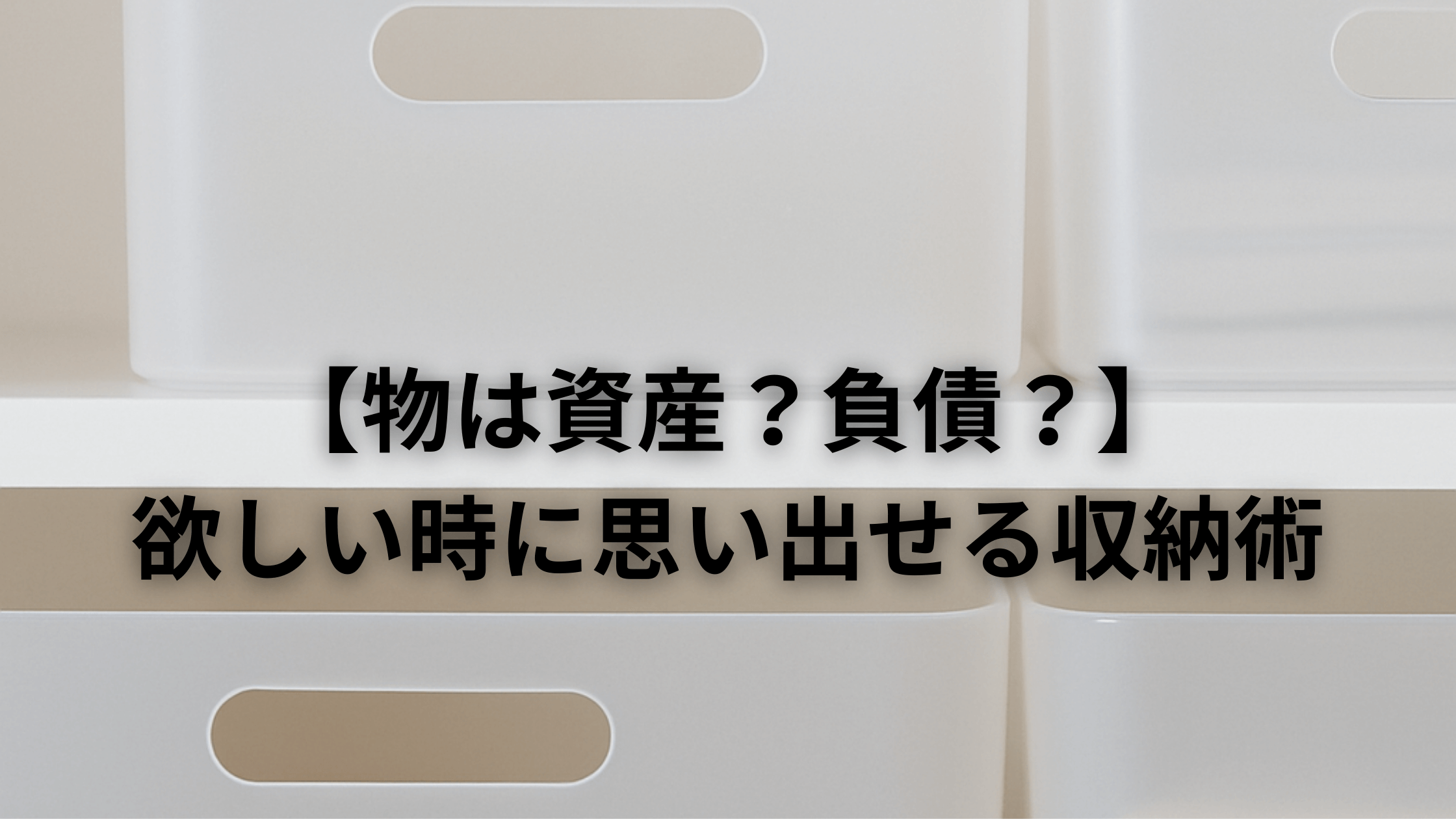
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4beb5da6.b4c158a8.4beb5da7.41c5347c/?me_id=1261641&item_id=10002782&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flivewell%2Fcabinet%2Fstorage2%2Fstorage2thumbnail%2Fimgrc0094969075.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


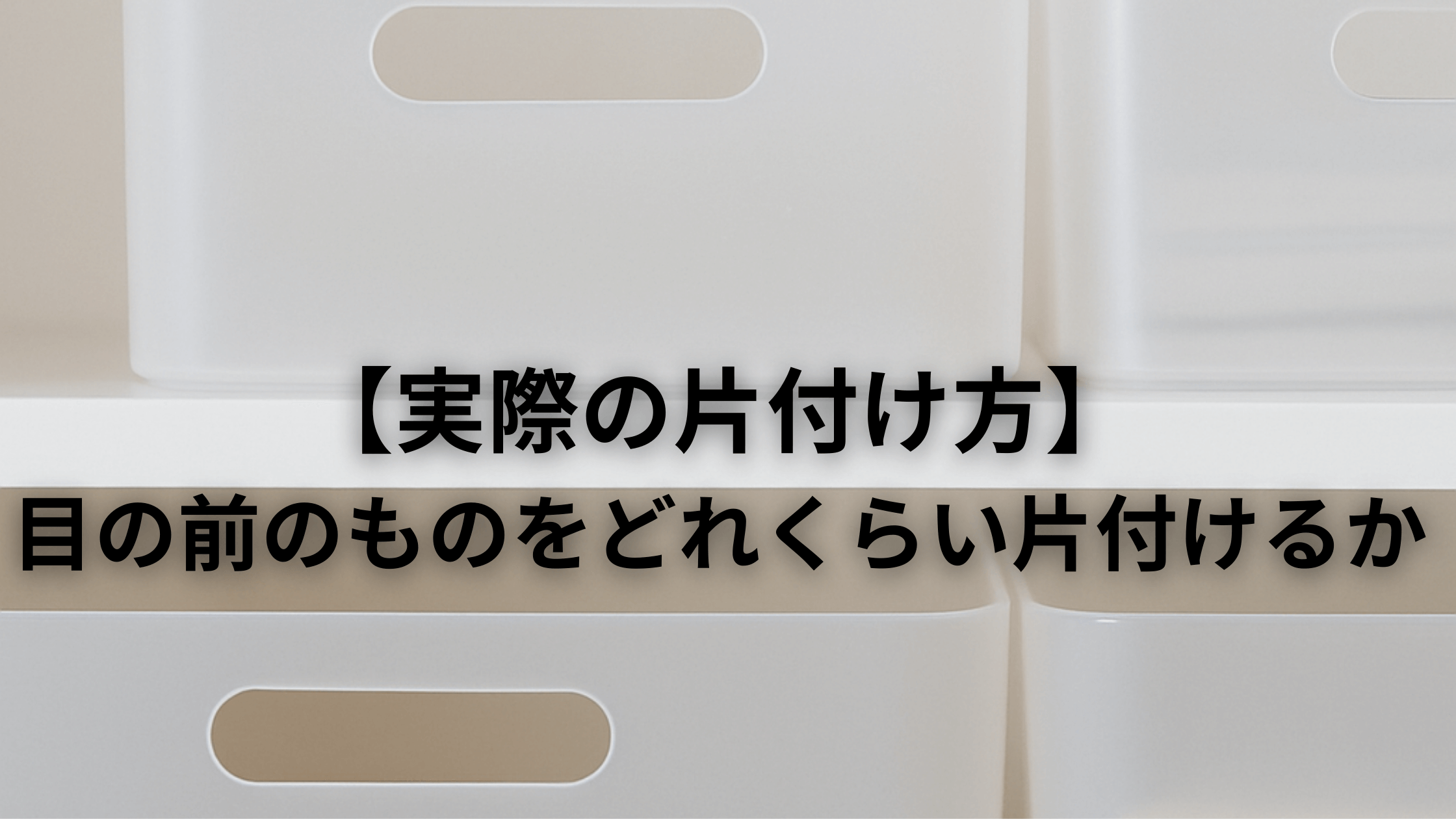
コメント